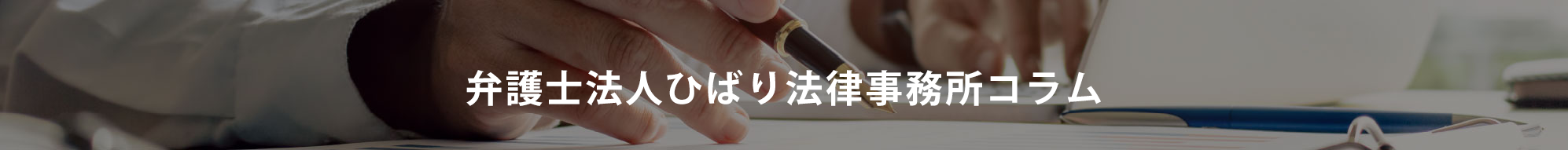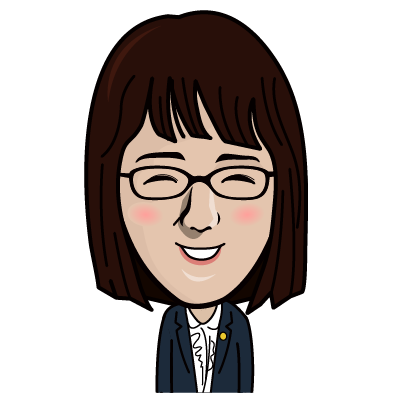個人再生で連帯保証人に及ぶ影響とできるだけ迷惑をかけない方法について
個人再生と連帯保証人への影響についてまとめました。連帯保証人がついている借金がある状態で個人再生した場合,連帯保証人は借金の残額を一括返済するよう求められます。しかし,連帯保証人がついている借金を隠したり,個人再生前にその借金だけを完済したりすることはルール違反になります。できる限り連帯保証人に迷惑をかけない方法についても概説します。
目次
個人再生で連帯保証人に及ぶ影響について
弁護士からの受任通知が債権者に届くと,その借金に連帯保証人がついている場合,債権者は,通常,連帯保証人に対して借金を一括返済するよう請求をします。連帯保証人の場合は債権者の請求を拒むことができません。再生手続前に連帯保証人が返済した場合には,求償権として本人へ請求ができますので,その債権も再生手続に組み込む必要があります。
(認可決定確定後に連帯保証人が債権者へ返済をしても,本人へ求償権の請求はできなくなってしまいますので,注意が必要です。)
「個人再生をすると,連帯保証人に迷惑をかけるのでは…」と不安になると思います。たしかに,個人再生手続をとると,原則として借金をしているすべての債権者が手続きの対象となります。保証人がついている借金だけを手続きから除外することはできません。
保証人とは,借金をした人が返済できなくなった場合,本人に代わって返済する法律上の義務を負う人です。保証人には厳密には「保証人」と「連帯保証人」があり,連帯保証人のほうが重い責任を負います。
一般的に,借金の保証人になるときは「連帯保証人」になることがほとんどです。そのため,この記事では,主に連帯保証人への影響について取り上げます。
借金に連帯保証人がいる場合でも,事前に準備をしておけば,連帯保証人に与える影響をある程度抑えることができます。また,借金問題は放置しているとどんどん深刻化していきますので,早めに弁護士に相談することで影響を軽減できる可能性があります。
連帯保証人への影響①借金の一括返済を請求される
個人再生をすると,連帯保証人はお金を借りた本人が免れた借金を一括で返済するように債務者から請求されます。
個人再生手続により,借金をした本人は,減額された債務について,原則3年(最長で5年)の分割払いで返済することになります。例えば,総額1,000万円の借金があり,個人再生をして200万円に減額する再生計画が認められた場合,その後3年かけて200万円を分割払いすれば借金はなくなります。
しかし,上記1,000万円の借金の中に,たとえば,100万円の借金について連帯保証人がついている場合,まず,この100万円について債権者は連帯保証人へ請求します。この段階では全額の返済義務が生じますが,最終的に,本人が再生計画に基づいて20万円返済した場合には,残り80万円について連帯保証人の返済義務が残っている状況となります。
もっとも,債権者と交渉して,分割払いへの変更が可能なケースがあります。たとえば,日本学生支援機構からの奨学金であれば,特別な事情がなければ,これまで通りの分割による返済内容で連帯保証人が返済していけば良いケースがほとんどです。
その他債権者など,連帯保証人自身での交渉が難しい場合には弁護士に任意整理を依頼することも一つの方法です。
【住宅ローン特則を使った場合】
例外的に,住宅ローン特則を利用した場合,住宅ローンの保証人は債権者から一括請求を受けずに済みます。(民事再生法203条1項,177条2項)。
住宅ローン特則は,個人再生における特徴的な手続きで,これを利用すると,住宅ローンについては支払いを継続することができ,借金圧縮の対象にはなりません。もちろん住宅ローンの残額は本人が全額支払わなくてはなりませんが,代わりにその住宅を手放さずに済み,保証人に迷惑をかけることもありません。
連帯保証人への影響②債権者の請求を拒めない
借金の連帯保証人となった場合,債権者から請求を受けたら,拒むことはできません。
保証債務には「保証人」と「連帯保証人」があり,「保証人」の場合は,以下の権利や利益が法律上認められています。
(1)催告の抗弁権(民法452条)
債権者が保証人に請求したときは,保証人は,まず本人に催告するよう主張する権利
(2)検索の抗弁権(民法453条)
保証人が,本人に弁済をする資力があり,かつ,執行が容易なことを証明したときは,債権者は債務者の財産について強制執行をするように主張する権利
(3)分別の利益(民法427条,456条)
保証人が複数いる場合,保証債務は,保証人の数で割っただけの金額を支払えばよいという利益
このように,保証人であれば,本人が大きな財産を持っていることを証明して返済を免れたり,他の保証人がいる場合は債務を頭数で割って支払ったりすることが可能です。
しかし,連帯保証人の場合,こうした抗弁はできませんし,連帯保証人が複数いても,債務の全額を支払うよう請求された際に拒むことができません。
連帯保証人への影響③返済後,本人に返還請求ができない
個人再生をすると,連帯保証人が本人に代わって借金を返済した場合,その後で本人に請求することができません。
原則として,連帯保証人が本人に代わって借金を支払った場合,自分が債権者に支払った金額を本人に求償できます。これを「求償権」と言います。
ところが,本人が個人再生手続きをとった場合には,求償権が認められません。本人の借金額は再生計画に記載された金額のみとなり,この再生計画を超える債務を本人が負うことはないのです。
連帯保証人がいる時に避けるべきこと
連帯保証人のついた借金があっても,その借金の存在を隠したり,個人再生前にその借金だけ優先的に弁済したりしてはいけません。どちらもルール違反の行為で,借金の減額幅が少なくなるほか,最悪の場合は個人再生手続ができなくなってしまう可能性があります。
(1)連帯保証人がいる借金を隠してはいけない
個人再生の際には,お金を借りている債権者のリストである「債権者一覧表」を作成して提出します。この際,法人・個人を問わず,借金をしている相手のことは漏らさず書かなくてはなりません。故意に債権者の存在を隠すと,裁判所から不誠実な申立てと判断され,申立てを棄却されたり,再生計画が不認可になったりするおそれがあります。
個人再生においては,「個人再生委員」という,裁判所が選任した弁護士が関与することがあります。東京地裁の場合は全ての個人再生で個人再生委員が選任されるほか,他の裁判所でも複雑な事案では選任されます。
個人再生委員は,債務者の保有する資産や銀行預金の取引履歴,家計の状況などを調査します。不審な取引履歴や,疑問を抱かせる状況が発覚した場合,合理的な説明を要求されます。個人再生委員は経験を積んだ弁護士ですから,素人が借金を隠してもすぐに見破ってしまうでしょう。
(2) 個人再生前に連帯保証人付きの借金だけ弁済してはいけない
「個人再生を始める前に,保証人がいる借金だけすべて弁済しておくのはどうか」と思われる方もいることでしょう。返済の目途がたたなくなった後に特定の債権者の借金だけを優先して弁済するのは,「偏頗(へんぱ)弁済」として禁止されています。
偏頗弁済が見つかると,最悪の場合は個人再生の申立てが棄却されます。棄却されない場合でも,清算価値への計上など手続きに影響を与えますので,やめましょう。
連帯保証人に迷惑をかけたくない場合に行うこと
保証人や連帯保証人に迷惑をかけたくない場合,(1)任意整理で解決できないか検討する,(2)第三者弁済をしてくれる人を探す,(3)保証人にも債務整理を検討してもらう,という3つの方法が考えられます。
(1)任意整理で解決できないか検討する
任意整理とは,裁判所の手続きによらないで借金負担を軽減する方法で,債権者と弁護士が交渉して利息のカットや返済計画の見直しなどを交渉します。
任意整理の特色として,「減額交渉する債権者を選べる」ことがあります。消費者金融や,連帯保証人のついていない借金だけを対象にして,保証人のいる借金を除外すれば,保証人に迷惑をかけることはありません。
任意の話し合いのため,過払金がない限り,大幅な借金減額は見込めませんが,3~5年程度の分割払いで支払いきれるのであれば,任意整理で解決できる場合もあります。
なお,本当に任意整理に適した事案かどうか判断するためには,弁護士に法律相談でアドバイスを求めたほうが良いでしょう。
(2)第三者弁済をしてくれる人を探す
連帯保証人に迷惑をかけない方法の一つとして,債務者本人以外の第三者に,連帯保証人がついている借金の残額を支払ってもらうことがあります。本来は支払う義務のない第三者が支払うことを「第三者弁済」と言い,これをしてくれる人がいれば,本人も連帯保証人も債務者に支払う必要がなくなります。
ただし,債務者の同居の家族など,債務者と生計を共にしている人は,偏頗弁済とみなされるおそれがあるので,注意が必要です。
第三者弁済の場合,本当に第三者が支払ったと証明できるような振込証明書などを作成・保管しておく必要があります。
また,第三者弁済を行った場合,その第三者が今度は「債権者」として個人再生手続きに参加します。第三者弁済をしてくれた人が再生手続きに関わる気がない場合は,「求償権を放棄する」という形で債権放棄をしてもらう必要があります。
(3)連帯保証人に債務整理を検討してもらう
任意整理も第三者弁済も難しければ,連帯保証人に事前に個人再生を行う旨を説明し,返済が難しい場合は連帯保証人にも債務整理を検討してほしいと伝えます。
本人が弁護士等に正式に依頼して個人再生の申立ての準備を始めると,連帯保証人に請求が行くこと,連帯保証の場合は請求を拒めないことなど事情を説明することが必要です。
連帯保証人にとっては,何の前触れもなく突然債権者から請求が来たら困ってしまいます。また,連帯保証人が借金を支払った場合には,個人再生手続の債権者となりますので,きちんと対応する必要があります。
個人再生後に保証人になれるのか?
個人再生後,原則として5~7年程度は他の人の借金の保証人になれません。しかし,例外的に賃貸住宅や奨学金の保証人であればなれる可能性があります。
個人再生をすると,信用情報機関という,個人の借金等の情報を記録する機関に個人再生の情報が記載されます(いわゆるブラックの状況)。
信用情報機関は国内に3つあり,金融機関や貸金業者はそのいずれかに加盟しています。保証人として契約を結ぶ際,金融機関等は信用情報機関の記録を確認するので,ブラックの場合には審査に落ちてしまいます。
したがって,信用情報機関に情報が記載される5~7年間は,保証人になることは難しいと言えます。
なお,信用情報機関の記録は,本人であれば開示請求が可能ですので,期間が経過したら個人再生の記録が消えているかどうかチェックするのも良いでしょう。
- 株式会社日本信用情報機構(JICC)
- 株式会社シー・アイ・シー(CIC)
- 全国銀行個人信用情報センター(KSC)
連帯保証人に迷惑をかけないためには早めに専門家に相談を
連帯保証人がついている借金があり,連帯保証人に迷惑をかけずに解決するためには,できるだけ早めに専門家に相談されることをお勧めします。
なぜなら,借金問題が比較的軽いうちは,任意整理で解決できる可能性があるからです。任意整理ならば対象の債権者を選べるため,連帯保証人がついている借金を対象外にすることで,連帯保証人に全く迷惑をかけずに借金負担を減らすことができます。
借金問題がより深刻でも,個人再生ができる段階であれば,保証人にかかる負担を減らせます。
自己破産以外に方法がないほど深刻化していた場合,債務者は自己破産すれば借金がゼロになりますが,連帯保証人には全額の支払い義務が残ります。
このように,借金問題に手を付ける時期が早ければ早いほど,保証人に迷惑をかけずにすむ可能性が高くなります。
ご自身のケースで,複数ある債務整理のどの手続きが適切かを検討するためにも,できるだけ早めに弁護士に相談されることをお勧めします。
東京弁護士会 登録番号 53737
困っている人を助けたい、という想いから弁護士を志しました。
女性でも相談しやすい環境をご用意していますので、お気軽にご相談ください。
【経歴】
明治大学法学部卒
明治大学法科大学院修了
東京弁護士会所属(司法修習68期)