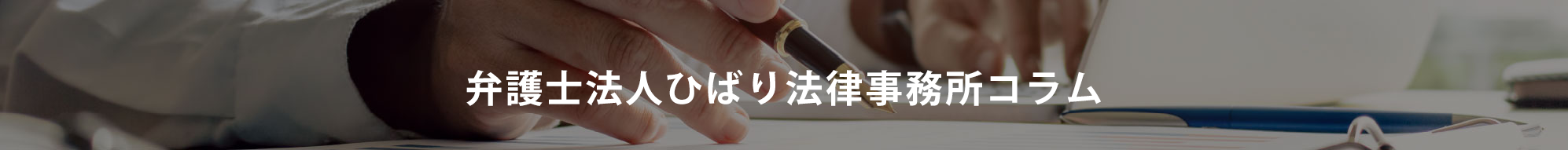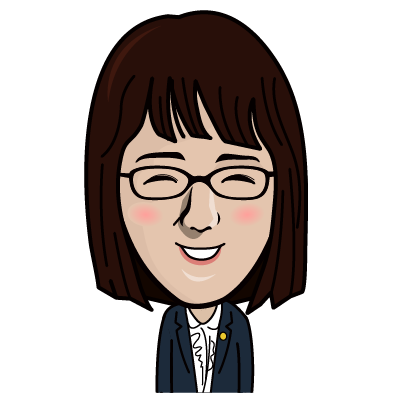個人再生すると住宅ローンはどうなる?特則を利用する条件とは
個人再生すると原則として住宅ローンも減額されますが,その場合抵当権が実行されて住宅を失うことになります。住宅を守るために住宅ローン特則を利用すると,住宅ローンは減りません。ペアローンの場合の特則の利用方法や,連帯保証人や連帯債務者はどうなるのか,住宅ローンを借り換えていた場合など,よくある問題についてまとめました。
目次
個人再生をすると住宅ローンは減額されるのか
個人再生をすると原則として住宅ローンも減額されますがその場合抵当権が実行されて住宅を失うことになります。通常,個人再生を行う方は,住宅は維持したい,その他財産は維持したいという希望があるかと思いますので,住宅を維持するために,「住宅ローン特則」を利用することになりますが,その場合は住宅ローンは減額されません。
個人再生は,裁判所を通した手続きにより,借金を大幅に減額できる制度です。減額できる割合は,債務額や資産の金額にもよりますが,債務総額の5分の1程度,債務額が多い場合は10分の1程度になることもあります。
個人再生の大きな特徴は,住宅ローンが残っている家を手放さずに,他の借金の減額ができる「住宅資金貸付債権に関する特則」(いわゆる住宅ローン特則)という仕組みがあることです。
(1)住宅ローン特則を利用した場合
住宅ローン特則を利用すると,住宅ローン自体は減額されません。その代わり,住宅に住み続けたまま,それ以外の借金を大幅に減らすことができます。
個人再生後の住宅ローンの返済計画に関しては,次のパターンがあります。①および②,③,④は先行する条項が可能な場合にはそちらを使います。
①期限の利益回復型
住宅ローンの遅滞に陥っている部分と,契約上の債務を計画期間内に弁済することで,再生手続開始決定前に発生している期限の利益喪失の効果を失わせるパターンです。
②そのまま型
原契約のまま住宅ローンの返済を続けるパターンです。住宅ローンについて期限の利益を喪失しておらず,申立後も住宅ローンについて一部弁済許可により返済を継続している場合には,原則としてそのまま型になります。
③リスケジュール型
①のパターンによる計画の認可の見込みがない場合,利息・損害金を含めて全額弁済をする前提に,支払期限を最大10年間,債務者が70歳を超えない範囲内で延長し,各回の支払額を減らすというものです。
④元金猶予期間併用型
③のリスケジュール型に加えて,計画案期間内は原本の一部の弁済の猶予を受け,一般再生債権の弁済と調和した弁済計画を可能とするものです。債務者が70歳を超えない範囲内という条件は③と同じです。
⑤同意型
債権者の同意を得て返済条件や期間を決定する方式で,①~④以外の内容でも,債権者から同意を得られれば可能です。
(2)住宅ローン特則を利用しない場合
住宅ローンを返済中でも,住宅ローン特則を利用せずに個人再生することはできます。この場合,住宅ローンも他の借金同様に大幅が可能ですが,自宅は抵当権が実行され競売にかけられます。マイホームは手放し,賃貸物件など別の住居に引っ越さなくてはなりません。
住宅ローンがペアローンの場合,住宅ローン特則は利用できるのか
ペアローンとは,住宅ローンのうち,住宅を購入する際に夫婦が持ち分に応じてそれぞれローンを契約することを言います。一人で申し込むより高額なローンを借りられるのがメリット。親子などのケースもありますが,ここでは夫婦,および,東京地裁の運用を想定して説明します。
※なお,住宅ローン特則の運用は,裁判所によって異なる場合もあります。また,具体的な状況によっても変動するため,地域の裁判所の運用に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。
本来,住宅の上に民事再生法第53条1項に規定する担保権が存するときは住宅ローン特則を利用できません。通常ペアローンはこれに該当することになりますが,そうすると,担保権が実行され,住宅を失うことになってしまいます。
そこで,夫婦同時申立の場合には,実質的に1つの申立ての中で,両方の計画案が同時に認可されることで,住宅ローン特則の効力により,担保権の実行が阻止されるという考え方により,夫婦同時申立の場合,いずれの手続きにおいても住宅ローン特則の利用を認める方向で運用されています。
夫婦のうち,どちらかが単独で申立てをする場合には,本来担保権実行のおそれがあるということになりますが,たとえば,夫のみの申立ての場合で,妻が住宅ローン以外に債務がないようなケースで,個人再生委員の意見も踏まえ,住宅ローンの負担内容,弁済状況,夫婦の収入状況,住宅ローンの債権者の意向など具体的事情により,住宅ローン特則の利用を認めたケースもあります。
ただし,あくまでケースバイケースであり,必ず認められるというものではありません。
住宅ローンがペアローンの場合の連帯保証人や連帯債務者はどうなるのか
ペアローンの場合,夫婦がお互いの住宅ローンについて連帯保証をしているケースがあります。
(1)ペアローンと連帯保証人
「①ペアローンで夫婦の片方だけ個人再生をする場合」と,「②ペアローンで夫婦ともに個人再生を行う場合」の2パターンが考えられますが,①②ともに配偶者に負担がかかるのは避けられません。
夫婦ともに借金をしている場合には共通した利益がある場合が多いと思います,どちらか片方だけが作った借金の場合,堅実に生きてきた方が手続きに巻き込まれる形になるので,夫婦関係に亀裂が入るおそれもあります。
①ペアローンで夫婦ともに個人再生を行う場合
夫婦で個人再生をする場合,住宅ローン特則が利用可能です。ただ,双方に対する保証債務履行請求権については一般の再生債権となり権利変更を受けることで,住宅ローン特則の利用の結果と矛盾が生じてしまいます。
このような場合に,再生委員の意見を踏まえ,双方の個人再生手続において,双方の保証債務履行請求権を住宅資金貸付債権として取り扱った事例もあります。
②ペアローンで夫婦の片方だけ個人再生をする場合
上記の通り,ペアローンで,夫婦の片方だけが申立てをした場合でも,状況次第では住宅ローン特則の利用が可能な場合があります。
この場合において,片方が住宅ローンの連帯保証人になっている場合,保証債務履行請求権については一般の再生債権となり権利変更を受けることで担保権実行のおそれがあります。
こういった場合には,事前に住宅ローン債権者と協議をして,連帯保証人の期限の利益を喪失させない旨同意を得る必要が出てきます。
住宅ローンを借り換えていた場合はどうなるのか
住宅ローンの借り換えを行っていたとしても,原則として住宅ローン特則の利用は可能です。新たに借りた住宅ローンも,「住宅資金貸付債権」に該当すれば,住宅ローン特則の利用に支障はありません。
※住宅資金貸付債権とは,住宅の建設若しくは購入に必要な資金,又は,住宅の改良に必要な資金で分割払いの定めのある再生債権であって,当該債権又は当該債権に係る債務の保証人の主たる債務者に対する求償権を担保するための抵当権が住宅に設定されているものを指します。
ただし,以下の場合は住宅ローン特則が利用できない可能性があります。
①借り入れの使途が住宅ローンの支払いではなくなっている場合
借り換えの契約において,借金の使途が「住宅ローンの支払い」でなくなっている場合は,住宅資金貸付債権に該当せず,住宅ローン特則が使えないことがあります。契約書をご確認ください。
たとえば,前住宅の残ローンも合わせて一体のローンとなっている場合に,住宅資金貸付債権に該当しないと判断される場合があります。
②借り換えの際の諸費用が住宅ローンに含まれている場合
ローンを借り換えた際の諸費用もローンに含まれている場合,住宅資金貸付債権に当てはまらないとして,住宅ローン特則が利用できないことがあります。
(借り換えの場合でなくとも,諸費用ローンが含まれている場合も同様です。)
個人再生中や個人再生後に住宅ローンは組めるのか?
個人再生中や,個人再生後5~7年間は住宅ローンを組むことはできませんが,この期間が過ぎれば,いわゆるブラックの状況は解消されます。
個人再生をすると,信用情報機関の記録に個人再生をした事実が記載されます。信用機関によって異なりますが,5~7年は登録されることになり,記録が残っている間は新たなローンが難しくなります。
信用情報機関とは,個人のお金の貸し借りや分割払いなど,個人の金融上の信用にかかわる取引のデータを記録する機関です。信用情報機関は日本に3つあり,金融機関や貸金業者,クレジットカード会社などは3つのうちどれかに加盟しています。
- 株式会社日本信用情報機関(JICC)
- 株式会社シー・アイ・シー(CIC)
- 全国銀行個人信用情報センター(KSC)
金融機関等は,新たな住宅ローンの申し込みを受けると,信用情報機関のデータを参考に審査を行います。個人再生は,当初の契約通りに借金を返済できなくなり,再生手続で減額してもらった記録ですから,お金を貸す側にとってはブラック情報(事故情報)となります。そのため,記録が削除されるまでは住宅ローンの審査には基本的に受からないと考えてください。
また,事故情報が消えるまでは,分割払いやクレジットカードの更新・利用も難しくなります。
以上
東京弁護士会 登録番号 53737
困っている人を助けたい、という想いから弁護士を志しました。
女性でも相談しやすい環境をご用意していますので、お気軽にご相談ください。
【経歴】
明治大学法学部卒
明治大学法科大学院修了
東京弁護士会所属(司法修習68期)