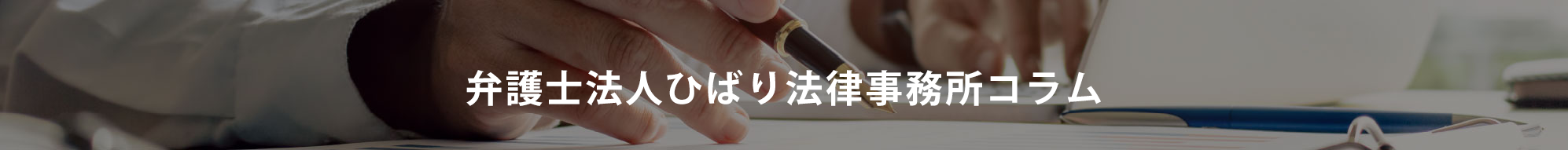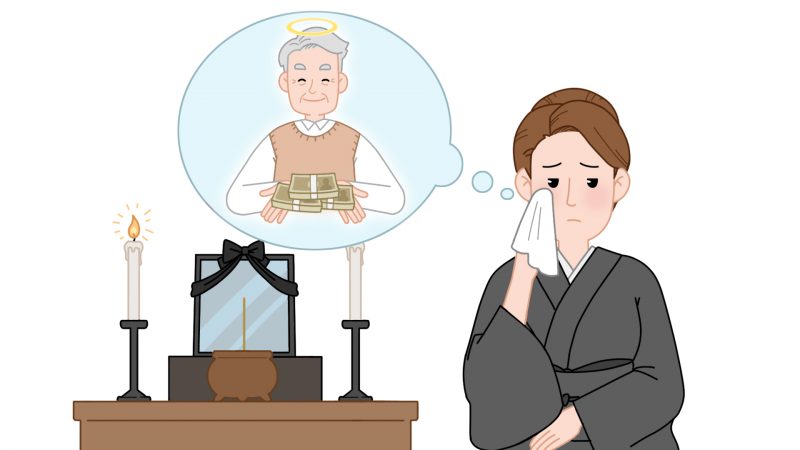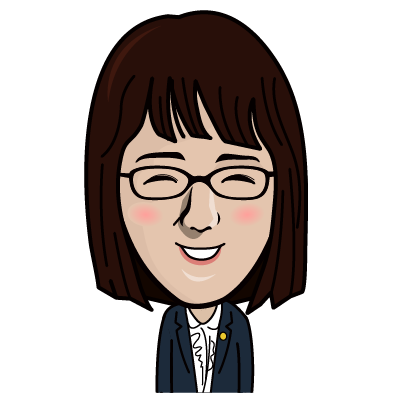自己破産時に生命保険を解約する必要があるケースと対処法
自己破産の際,貯蓄型の生命保険(定期保険,終身保険,養老保険,学資保険,年金保険など)で,20万円を超える解約返戻金がある場合は,生命保険を解約しなくてはいけない可能性があります。生命保険を続けられない理由や,解約になる保険の種類,条件について詳しく解説します。生命保険の解約が必要ないケースや,生命保険を解約したくない場合の対処方法についてもまとめました。生命保険契約の存在を裁判所に隠すと,自己破産に失敗するおそれがあるので,絶対に行わないようにしましょう。
目次
自己破産で生命保険を解約しなければいけない場合とは?
自己破産の際,全ての生命保険を解約しなければならないわけではなく,次の2つの条件に両方当てはまる場合にのみ解約が必要です。
(1)貯蓄型(積立型)の生命保険である
(2)解約返戻金が20万円以上発生している
生命保険は,保険期間中に死亡,もしくは高度障害状態になった場合に保険金が支払われる契約で,掛け捨て型と貯蓄型(積立型)に2種類に大きく分かれます。
自己破産の際,問題となるのは貯蓄型の生命保険です。なぜなら,貯蓄型は解約をするとそれまで積み立てたお金が戻ってくるため,保険に長期に加入していると高額な財産となるケースがあるからです。
自己破産手続をすると,一定額以上の財産は裁判所によって処分・換価され,債権者に配当される仕組みになっています。一定額とは,裁判所にもよりますが,東京地裁など多くの裁判所では「20万円以上」とされています。
従って,解約返戻金が20万円以上ある生命保険は原則として処分対象となり,破産管財人が解約して債権者に配当するルールになっています。
解約返戻金の返還率は,保険会社や契約の内容によっても違ってきます。一般的には,過去に支払った保険料合計の約7割程度といわれています。現在の解約返戻金の額を確認するには,保険証書を確認するか,保険会社に問い合わせると良いでしょう。
※複数の保険に入っている場合
貯蓄型の生命保険に複数加入している場合,全ての契約の解約返戻金の総額が20万円を超えている場合は,裁判所による処分対象となります。
※損害保険でも解約返戻金がある場合は処分対象になる
生命保険に限らず,解約すると未経過分の保険料が解約返戻金として払い戻されるタイプの損害保険も処分の対象になるため注意が必要です。火災保険や自動車保険なども該当する可能性があります。
心当たりがある場合は契約書を確認するか,保険会社に問い合わせてみましょう。
生命保険の解約が必要ないのはどういう生命保険か?
生命保険のうち,以下に当てはまるものは,原則解約する必要がありません。
(1)掛け捨て型の生命保険
(2)貯蓄型でも,解約返戻金の総額が20万円を下回る場合
掛け捨て型の生命保険の場合,ほとんどの場合では解約返戻金は無いか,あってもごくわずかなため,裁判所の処分対象になりません。
貯蓄型の生命保険の場合も,契約してからまだ期間が経っておらず,解約返戻金が20万円に満たない場合は,処分されることはありません。念のため,正確な解約返戻金の額を保険会社に問い合わせておくと安心です。
このように,自己破産をしても手元に残しておける財産のことを「自由財産」と言い,家財道具などの生活用品のほか,売却・換価しても20万円に満たない財産は自由財産になります。
なお,仮に,解約返戻金がない保険であっても,家計状況において,保険料の支払いがあまりに多い場合には,保険継続の必要を考えなければならないケースもあるでしょうk。
※国民年金保険,国民健康保険などの公的な保険は処分の対象外
公的年金や国民健康保険は自己破産によって処分されません。ただし,公的年金を既に受け取っている場合は,現金や預金として扱われ,金額によっては換価処分の対象になります。
生命保険の解約が必要になる理由
生命保険の解約が必要になる理由は,20万円以上の解約返戻金がある生命保険は財産とみなされ,解約返戻金を債権者に配当する手続きがなされるからです。
自己破産は,借金の返済義務を免れる強力な手続きですが,お金を貸した債権者はお金を取り戻せなくなります。国から補償を受けられるわけでもありません。そのため,少しでも損失を補填できるよう,破産者に一定額以上の財産がある場合は現金化して債権者に配当するルールになっています。
処分の対象となる財産は,主に以下のものです。
(1)土地・住宅などの不動産
(2)99万円を超える現金
(3)換価や売却をした際に20万円を超える価値がある財産
生命保険の解約返戻金が20万円を超える場合,(3)の財産に当てはまります。そのため,自己破産をすると保険を解約することになります。
具体的な手続きとしては,財産のある人が自己破産をすると,管財事件という手続きになります。裁判所によって「破産管財人」が選任されます。破産管財人は,破産者の財産を管理し,処分する権限を持ち,破産事件に詳しい弁護士が担当します。この破産管財人が保険契約を解約して解約返戻金を債権者に配当します。
※すでに満期が到来している,あるいは直近に到来する場合には,満期保険金を破産財団に組み入れることになります。
生命保険を解約したくない場合の対処方法
生命保険をどうしても解約したくない場合,いくつかの対応策がありますが,自己破産手続きのルールに違反しないよう,事前に専門家に相談して慎重に行ってください。
生命保険の契約内容は年齢や健康状態によっても異なるため,一度解約してしまうと,従前と同じような内容で再加入することは難しく,長年加入して来た貯蓄型保険を解約したくないという方もいることでしょう。生命保険を守りたい場合は,以下の方法が考えられます。
(1)保険法の「介入権」を利用する
(2)自由財産の拡張を認めてもらう
(3)契約者貸付制度を利用して解約返戻金を20万円以下にする
(4)破産管財人に解約返戻金相当額を支払う
(5)自己破産以外の債務整理を検討する
(1)保険法の「介入権」を利用する
生命保険の受取人に指定されている親族が,保険会社に解約返戻金を支払うことで,自己破産による解約を免れ,契約を継続できます。これを「介入権」といいます。
以前から,自己破産をした本人の配偶者や子供等の受取人を保護するため,自己破産をした人の生命保険を継続できないかという議論がありました。2010年の保険法施行に伴い,解約返戻金相当額を親族が用意できれば,生命保険契約を維持できることになりました。
受取人の親族と相談のうえ,介入権が利用可能であれば,弁護士に問い合わせされると良いでしょう。
(2)自由財産の拡張を認めてもらう
20万円未満の財産は自由財産となり,手元に置くことができます。しかし,20万円を超える財産であっても,裁判所が自由財産の拡張を認めれば,引き続き所有することが破産法34条4項で認められています。
【破産法34条4項】
4 裁判所は,破産手続開始の決定があった時から当該決定が確定した日以後一月を経過する日までの間,破産者の申立てにより又は職権で,決定で,破産者の生活の状況,破産手続開始の時において破産者が有していた前項各号に掲げる財産の種類及び額,破産者が収入を得る見込みその他の事情を考慮して,破産財団に属しない財産の範囲を拡張することができる。
自己破産の拡張は,あくまでも生活に必要不可欠な場合にのみ認められます。また,自動的に適用されるのではなく,自由財産の拡張を裁判所に申し立てる必要があります。その際,破産者側が自由財産の拡張を認めるべき理由や事情を説明しなくてはなりません。
自由財産の拡張が生命保険にも認められるかどうかは,解約により生活に支障が出るか否かによって判断されます。例えば,現在病気にかかっていて保険金を頼りに生活しているケース,持病により再度の保険契約の締結が難しいようなケースでは,自由財産の拡張が認められることがあります。
自由財産の拡張は,誰でも簡単に認められるという制度ではないので,事前に弁護士とよく相談して申し立てることになるでしょう。
(3)契約者貸付制度を利用して解約返戻金を20万円以下にする
生命保険の契約内容によっては,「契約者貸付制度」が利用可能なことがあります。これは,生命保険の契約者が,解約返戻金の範囲内でお金を借りることができる制度です。この制度を利用して解約返戻金の額を20万円以下にすれば,自由財産として認められる可能性があります。
もっとも,この方法は破産法のルールに抵触する可能性があるため注意が必要です。本来は債権者へ配当されるべき資産を減らしていることになりますので,
あとで裁判所に借りたお金の使途を説明しなければならないため,弁護士費用,税金等など,必要不可欠なこと以外には利用しないようにしましょう。事前に弁護士に相談されることをおすすめします。
※ただし,契約者貸付を利用している保険の場合,貸付金の利息の負担を回避するため,解約せざるを得ないケースもありますので,一長一短となります。
(4)破産管財人に解約返戻金相当額を支払う
自己破産手続にあたっては,破産管財人が財産の処分権限を持ちますが,通常は債務者の意向を確認しながら進めていきます。破産管財人に,生命保険をどうしても継続したいという希望を伝え,かつ,解約返戻金と同額を破産管財人に支払うことで,保険の継続が認められることがあります。
(5)自己破産以外の債務整理を検討する
生命保険など,どうしても手放したくない財産がある場合は,自己破産以外の債務整理を行う方法があります。債務整理には,自己破産のほかには「任意整理」と「個人再生」があります。
①任意整理
弁護士が債権者と私的に交渉をして,利息カットし,分割での支払いを協議する方法。借金を大きく減額はできませんが,同居の家族にもバレずに手続きできるなど,社会的な影響が少なくて済みます。
②個人再生
裁判所で手続きをして,借金を原則5分の1程度に大幅にカットする方法。20万円以上の財産のほか,ローン支払い中の住宅も守ることができます。債務整理の中でも煩雑で時間がかかるため,事前に弁護士に相談して準備を進める必要があります。
自己破産以外の債務整理では借金をゼロにはできず,減額後の債務を支払っていくことになります。①任意整理も②個人再生も,将来にわたって継続した安定収入があり,収入のうち一定額を借金返済に回すことができる人向けの手続きです。
現在,自己破産を真剣に検討している人の場合,比較的借金問題が軽い人向けの任意整理より,個人再生が適しているケースが多いでしょう。しかし,無職の場合や,借金額(住宅ローンを除く)が5,000万円を超えている場合は個人再生では対応できません。
詳しくは,弁護士に問い合わせて適切な手続きを選ばれることをおすすめします。
生命保険契約を隠すのはNG
生命保険を解約されたくないからと,自己破産の際に裁判所に申告せずにいると,「財産隠し」として,発覚した際に免責がおりなくなるおそれがあります。免責とは借金の返済義務を免れることを言いますので,免責許可が下りないと自己破産をしても借金がそのまま残ってしまいます。
法律上,免責が認められなくなるケースを「免責不許可事由」と言い,破産法252条1項
に定めがあります。
【破産法252条】
裁判所は,破産者について,次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には,免責許可の決定をする。
一 債権者を害する目的で,破産財団に属し,又は属すべき財産の隠匿,損壊,債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと。
破産管財人は破産のプロですから,銀行通帳などの収支をつぶさに調べ,疑問点がある場合は破産者に問い合わせます。素人が行うような財産隠しは簡単に見破られ,裁判所に露見してしまうでしょう。
(もっとも,通常保険料の支払いは,課税証明書や源泉徴収票に記載がありますので,そもそも隠すということ自体が困難でしょう。)
さらに,悪質だと判断された場合は破産法265条の詐欺破産罪に問われる可能性があります。有罪になれば10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金が科せられるので,財産隠しは絶対に行わないでください。
生命保険の取り扱いなど自己破産の相談は弁護士へ
自己破産をすると原則として20万円以上の解約返戻金がある生命保険は解約することになりますが,前述のように,場合によっては生命保険を継続できることがあります。
最終的な判断は裁判所(管財人の意見含む)次第になりますが,生命保険をどうしても継続したい事情がある場合,自己破産手続の前にその事情を詳しく弁護士に相談してください。
借金問題は,誰にも言えず一人で抱え込んでいるのが一番よくない状態です。誰かに話を聞いてもらうだけで,解決策が見えてくる場合もあります。
弁護士に相談するのは敷居が高く感じるかもしれませんが,まずは気軽に無料相談を利用されることをおすすめします。
東京弁護士会 登録番号 53737
困っている人を助けたい、という想いから弁護士を志しました。
女性でも相談しやすい環境をご用意していますので、お気軽にご相談ください。
【経歴】
明治大学法学部卒
明治大学法科大学院修了
東京弁護士会所属(司法修習68期)