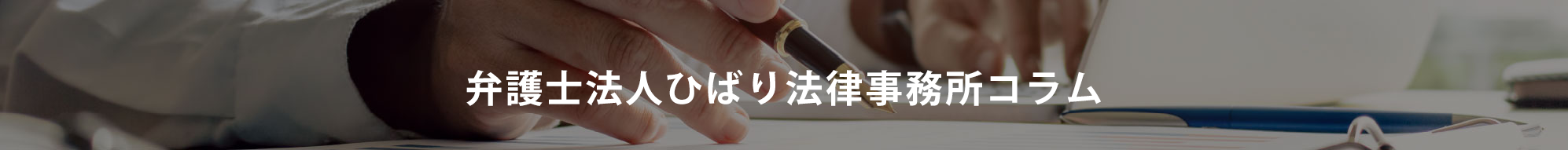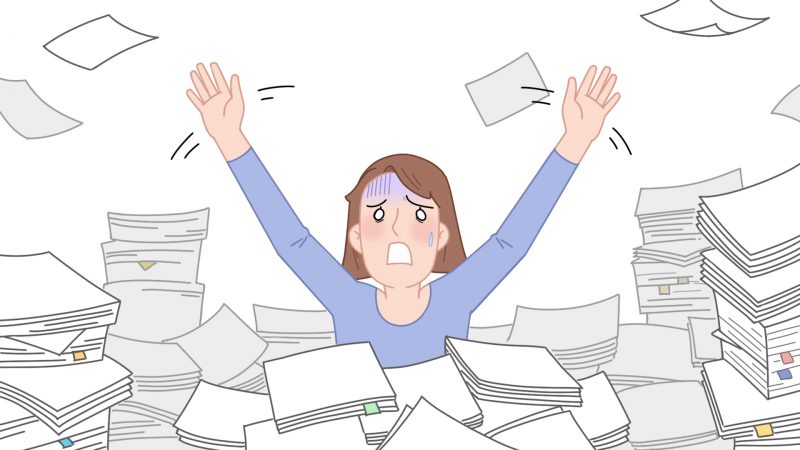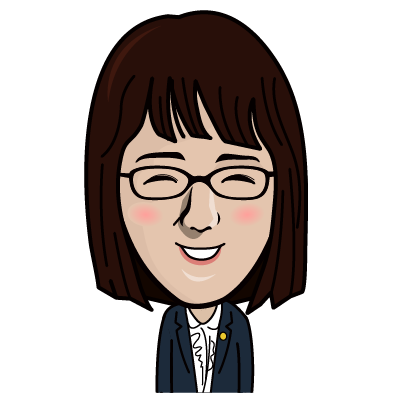個人再生に必要な書類と不備なく準備するためのポイント
個人再生に必要な書類や,準備にあたって何が必要かを概説します。個人再生には多岐にわたる書類が必要で,ひな型に沿って作成する書類と,役所等から取り寄せる書類があります。個人再生手続が開始されてから作成する書類もあり,特に再生計画案は締め切りが厳格なため注意が必要です。
目次
個人再生に必要な書類
個人再生手続のためには,大きく分けて(1)申立書や債権者一覧表などのひな形に沿って申立人が作成する書類,(2)住民票の写しや給与明細といった申立人が取り寄せる書類の2種類があります。
個人再生は,基本的には申立人の住所地を管轄する地方裁判所に申し立てて手続きを進めます。その大きな流れや,主要な必要書類は変わりませんが,手続きの具体的な運用は地方裁判所ごとに大きく異なることがあります。こちらでは,利用者がもっとも多い東京地裁の運用をベースに紹介します。
給与所得者で小規模個人再生を行う場合,主に必要となる書類は以下の通りです。
- 再生手続開始申立書
- 住民票の写し
- 収入一覧および主要財産一覧
- 債権者一覧表
- 財産目録(一覧と細目)
- 家計全体の状況(家計収支表)
- 報告書
- 清算価値算出シート
- 委任状
- 再生債務者の収入額を明らかにする書類(給与明細,源泉徴収票他)
- 銀行通帳の写し
- その他財産の資料(例:退職金の見込み額を証明する書類)
この他に,住宅ローン特則(住宅資金特別条項)を利用する場合は,住宅ローンに関する資料および該当不動産に関する必要書類を提出しなくてはなりません。
必要な書類の入手先は,書類によって異なりますが,地方自治体,勤め先や金融機関など多岐にわたります。収集が大変な場合もあるかと思いますが,必要書類が集められないと申立てができなくなってしまいますので,しっかり対応することが大切です。
雛形がある書類
東京地裁に個人再生を申し立てる場合,基本的に日弁連が公表しているフォーマットが利用されます。一般的に「東京地裁モデル」と呼ばれており,どなたでもダウンロードして利用できます。
日本弁護士連合会:個人再生手続参考書式(https://www.nichibenren.or.jp/legal_advice/oyakudachi/kojinsaisei.html)
以下,ひな型に沿って再生する書類について紹介します。
・再生手続開始申立書
個人再生の手続を開始してほしいと裁判所に申し立てるための書類で,小規模個人再生用と給与所得者等再生用があります。
・収入一覧および主要財産一覧
給与や賞与の額,主要財産の一覧を作成して記入します。財産には,例えば退職金見込額や持っている不動産の評価額などを記入します。
・債権者一覧表
債権者の名前・住所と,債権の種類,債権額,利率などを記入します。
住宅ローン特則を利用する場合は,個人再生申立て時に債権者一覧表に住宅ローンの債権に関する記載と,住宅ローン特則を利用する予定であることを書式に沿って記入する必要があります。
・財産目録(一覧と細目)
財産目録は「一覧」と「細目」に分かれ,「一覧」には弁護士預かり金,預貯金,退職など17の項目について,財産の有無を正直に記します。該当する財産がある場合は,「細目」に具体的に記入します。
・家計全体の状況(家計収支表)
申立て前2ヶ月分の家計の状況について,世帯全体の収支を記載します。
・清算価値算出シート
清算価値算出シートとは,申立人の財産のうち,生活必需品などの自由財産を除く財産を換価処分したと仮定した場合,どのくらいのお金になるのかを計算するシートのことです。
・(給与所得者等再生の場合)可処分所得額算出シート
給与所得者等再生を利用する場合には,可処分所得の金額を算出します。弁護士に依頼している場合は資料をもとに弁護士が作成することになります。
自分で集める書類
申立人が自分で集める書類の主なものを紹介します。場合によっては他にも書類が必要になることがあります。
・住民票の写し
裁判所が,申立人の住所を確認して,管轄があることを確認するための資料です。
・委任状
弁護士を選任している場合,裁判所に委任状を提出します。これにより,弁護士は申立人の代理人として活動できるようになります。通常は,法律事務所に所定の書式があるので,申立人の住所と氏名を記載して押印します。
・再生債務者の収入額を明らかにする書類(給与明細,源泉徴収票他)
給与明細は最新2ヶ月分の給与とボーナス,源泉徴収票は過去2年分を提出します。確定申告を行っている場合は確定申告書の提出も必要です。
・銀行通帳の写し
原則として過去2年分の通帳の写しを提出します。
・退職金の見込み額を証明する書類
今の時点で退職した場合に,どのくらいの退職金が出るのかを証明する書類です。会社に頼んで「退職金見込額計算書」を作成してもらいます。
状況によって提出が必要な書類
申立人が以下のケースに当てはまる場合,状況によってはこれらの書類が必要になることがあります。
- 車を持っている場合…車検証
- 生命保険や医療保険に加入している場合…保険証券
- 賃貸住宅や社宅に住んでいる場合…賃貸契約書や社宅証明証
- 年金受給者…年金通知書
- 児童手当の給付を受けている場合…児童手当の支払通知書
- 不動産を所有している場合,不動産の査定書2社
- その他財産について報告する必要があるものについての資料
住宅ローン特則を利用する場合の必要書類
民事再生法196条に規定されている住宅資金特別条項(いわゆる住宅ローン特則)を利用すると,住宅ローン返済中の不動産を手放さずに個人再生をすることが可能です。この場合,下記の書類の提出が必要になります。(民事再生規則第102条)
・住宅ローン契約書の写し
住宅資金貸付契約の内容を記載した書類と,返済期間や返済額が書かれている書面(償還表)が必要です。
・住宅及び住宅の敷地の登記事項証明書(共同担保目録付き)
登記事項証明書は,全国の市役所庁舎などに設置されている「法務局証明サービスセンター」の窓口で発行してもらえます。また,「登記・供託オンライン申請システム」という,オンラインで登記事項証明書の請求ができるサービスもあります。
発行日から3か月以内の原本が必要となります。
・その他の必要書類
以下のケースに当てはまる場合は,状況に応じた書類が必要になります。
- 自己の居住の用に供されない部分がある場合…居住している部分と,居住用でない部分の床面積を明らかにする書面
- 保証会社がついている場合には,保証委託契約書
など
個人再生申立後の必要書類
個人再生の際は申立て時だけではなく,手続き中にも書類の提出が必要です。特に,再生計画案は期日に一日でも遅れてしまうと個人再生に失敗してしまうので注意しなくてはなりません。
・財産状況等報告書
申立てから約10週間後をめどに提出する書類で,ほとんどの場合,申立て時に提出した「財産目録に記載の通り」という欄にチェックして提出します。例外的に,申立て後に財産状況が変化した場合は,変動内容を記載します。
また,報告書には,過去10年の職歴及び家族関係,住居の状況,個人再生手続きを申し立てるに至った事情について記載します。過去7年以内の自己破産や給与所得者個人再生,ハードシップ免責の有無についても記入します。
・債権認否一覧表
個人再生手続が開始すると,裁判所は各債権者に対し,手続開始決定書とともに,債権者一覧表を送付します。債権者はこれを確認し,債権額などに誤りがあれば,債権届出期間内に債権届出書を裁判所に提出します。
債権者に特に異議がなければ届け出をする必要はなく,期間経過後に債権者一覧表に記載された通りの内容で確定します。
債権認否一覧表は,債権者の認否をまとめた表で,債権者からの届け出の有無を確認後に作成するため,申立てから約10週間後に提出します。
・異議書
債権者が異議を唱えた債権がある場合,申立人は債権者に事前に通知の上,裁判所に異議書を提出し,またその写しを個人再生委員に提出します。異議書の提出が無いと,債権認否一覧表に債権の内容を認めない旨を書いても,異議がないものとみなされる可能性があります。
・再生計画案
再生計画案は,裁判所が個人再生を許可するかどうかを判断する非常に大切な書類です。
個人再生手続が開始されると,個人再生委員との面談が行われ,問題なしと判断された場合,裁判所が開始決定を出し,その後スケジュールに沿って書類を提出していきます。債務額および清算価値等を確認し,基準となる返済総額を決め,再生計画案を作成していくことになります。
再生計画案には,債務額や清算価値などから算出した最低弁済額と,原則3年(最長で5年)で借金の残額を分割払いする計画を記載します。裁判所はこの再生計画を審査して,計画されたとおりに弁済が可能と判断した場合は再生計画を許可します。
再生計画案の提出時期は裁判所によっても異なりますが,概ね申し立てから18週間後に提出します。再生計画案の締め切りは厳格で,期日に一日でも遅れると個人再生手続が廃止されます。せっかく費用と時間と手間をかけたにもかかわらず,借金が減額できなくなりますので,必ず締め切りを守るようにしてください。急な事情があってどうしても期日内に提出が難しい場合は,期限の伸長が可能ですが,必ず提出期間内に申し出てください。
弁護士を代理人にしている場合には,基本的に弁護士が再生計画案を作成し,裁判所へ提出します。弁護士からの指示に従い,書類などを期限までに提出していけば問題ないでしょう。
書類の不備をなくすために
個人再生に必要な書類は多岐にわたるため,漏れなく用意するのが難しい場合があります。書類によっては代わりになる書類であれば裁判所が認めるケースがありますので,不明点は積極的に弁護士に相談して揃えていきましよう。
例えば,「源泉徴収票」を紛失したのであれば,課税証明書を代わりに提出することで申し立てが認められることがあります。(源泉徴収票の再発行を求められる場合もあります。)
また,退職金がある場合,会社に「退職金見込額計算書」を作成してもらう必要がありますが,会社に個人再生を行ったことを知られたくないケースもあるでしょう。自己破産と違い,個人再生には職業の資格制限はありませんが,お金の管理をする仕事などであれば,評判が落ちることが気になるケースもあると思います。
そうした場合は,会社の就業規則の写しなど,退職金計算の根拠が確認できる書類があれば問題ないケースがほとんどです。
裁判所に提出すべき書類に不備があったり,書類に虚偽の内容が記載されていたりすると,その程度によっては再生手続が廃止され,借金が減額されなくなるおそれがあります。
また,その程度に至らない不備であっても,裁判所から補正を命じられ,余計な手間や時間がかかります。また,申請書類は再生手続開始決定が出た後は訂正できないため,申立ての時点で十分に調査や検討を行い,正確で不足のない書類作成を心がけなくてはなりません。
書類作成の準備が不安な場合は弁護士に相談を
必要書類の多い個人再生の書類の準備を,全て申立人が一人だけで行うのは大変です。正確で確実な手続きの成功のためには,弁護士に相談して助言やサポートを受けながら手続きを進めましょう。また,申立代理人がついていない場合には,個人再生委員費用が通常より多くかかることがほとんどです。
また,再生計画案を練る際は,自分の考えだけでなく,債務整理の経験豊富な弁護士にアドバイスをうけることで,現実的な返済計画を策定できるようになります。
個人再生は,裁判所手続き期間だけでも約半年はかかります。申立てまでに弁護士費用の積み立て,書類収集を行いますので,それも含めると1~2年程度かかるケースもあります。
手続きには正確な書類提出が大切ですので,債務整理の経験豊富な弁護士の力を借りることをお勧めします。
また,そもそもの前提として,債務者の状況に照らして,個人再生手続をとることが最善かどうかという問題もあります。ケースによっては,よりシンプルな手続きである任意整理で解決可能なケースや,自己破産をしたほうがよいケースもあります。
任意整理であれば,裁判所を通さないので,上記のような多岐にわたる書類の準備は必要ありません。
ご自身の状況に合った債務整理を選ぶという意味でも,事前に弁護士に相談されることをお勧めします。
東京弁護士会 登録番号 53737
困っている人を助けたい、という想いから弁護士を志しました。
女性でも相談しやすい環境をご用意していますので、お気軽にご相談ください。
【経歴】
明治大学法学部卒
明治大学法科大学院修了
東京弁護士会所属(司法修習68期)